POCG1325

・・・少年時代のアバドが「指揮者になればこの曲を演奏できる」と思ったその曲がドビュッシーの「夜想曲」だった、という話はいろんなところで紹介されているので彼のファンならば周知の事実と思う。
そんなわけ?で、彼の録音歴の中では比較的早期にとりあげられているが、アバドとしてはめずらしくボストン交響楽団との録音になった(事情は知らない)。
「祭り」でのリズム感と「海の精」での女声合唱との繊細なバランス感覚の良さが印象に残る演奏。
後年のアバドの演奏と比べたらまだまだ、という部分は随所にあるものの、若々しさと勢いの点では今でも十二分に存在価値があると思う。
・「牧神の午後への前奏曲」
・管弦楽のための映像〜第2曲「イベリア」

ロイド(牧神の午後〜)
・「選ばれた乙女」・・・日本語の訳題についてはいろんな意見があるようだが、ここではこう表記する。穏やかな管弦楽、澄み切った女声合唱、そしてエモーショナルなソロイストの3者を的確にまとめあげる指揮者。極めて美麗な曲なのだが、その中に深い印影がくっきりと描き出された名演と思う。
・「牧神の〜」・・・独奏フルートの音色が若干重めに感じられなくもないが、演奏全体のバランスは決して悪くない。また、「このアルバムの中でこの位置に収録されている」というか、前後の2曲とのバランスも考慮した解釈のような気もする。指揮者はかなり派手に煽っているのだが品が悪くならないのはさすがと言うべきか。
・「イベリア」・・・甘美でアンニュイな情熱とリズミカルで色彩感あふれる音楽を上品に表現した名演。ラヴェルの「ボレロ」や「スペイン狂詩曲」、ビゼーの「カルメン」も含めて、アバドにとって「フランスの作曲家によるスペイン風味の曲」は、スウィートスポットに来るのかも知れない。
「ペレアスとメリザンド」

ファン=ダム(ゴロー)、クールティス(アルケル)、
ルードヴィヒ(ジュヌヴィエーヴ)、パーチェ(イニョルド)、
マッツォーラ(医者)、
ウィーン国立歌劇場合唱団
指揮の精緻さと清澄さ、音色と音量のデリケートな調整、しかも、必要な場面では故意に「醜い音」を美麗に出し切る穏やかな思い切りの良さ・・・そもそもウィーンフィルはそういう楽団ではないだろうと言われたらそれまでだが、アバド/WPの「フランスもの」をもっと聴いてみたかったな、と思いたくなるみごとな演奏。
おとなしそうでミステリアスなメリザンドのメリザンドのユーイング、一見好青年だけど実は・・・のペレアスのル・ルー、そして、難役のゴロー(トウが立ってしまった高貴な王子の、抑え切れない激しい嫉妬心、ってそれ自体すごくセクシー(笑)ですよね)を柔らかなダンディな声と常に複雑な陰が差す演技で演じきったファン=ダム、と主要キャストは文句なし。ファン=ダムと堂々と対峙するイニョルドのパーチェ、目だたないようで何もかもお見通し?のアルケルを優しく「歌う」クールティス(第4幕第2場の、メリザンドに対する、或る台詞がさまになるのが地味ながら凄いと思う・・)、ベテランの貫禄をみせるジュヌヴィエーヴのルートヴィヒ、と脇役陣も充実。
・・・幻想的というより童話的な、しかしその実かなり不健全で不明瞭な設定とストーリー、優しく美しく穏やかな音楽が心地よく続くが、歌手はほとんど「歌わ」ず、抽象的な会話を延々と続ける・・・ほかのことでは知ったかぶりを重ねてなんとかこんなサイトを作っているこの私にして、それがほぼ完璧に通用しない、というより、知ったかぶって何かを語ろう、という気力まで萎えさせる作品(苦笑。だが、もちろんドビュッシーや「ペレアス」への褒め言葉である。念のため)。
でも、それでも、知ったかぶることにして聴いてきて、
で、終曲。
「話がわかったかね?」「さっぱり(汗)」
・・・わかった(つもりな)のは、とりあえず、アバドがWPとこの曲を録音していて良かったな、ということ。
TOCE55078
独奏者・指揮者ともセンシティヴにしかしゆったりと鷹揚に、ある意味ドビュッシーらしく進行するが、正直、「自然な」感触に乏しく、なにか、良くない意味で「頭で組み立てた」ような印象が強い曲(演奏が、ではなく曲が、である)。
ただ、これを、本アルバムでのモーツァルトと武満とをつなぐ「間奏曲」と考えたときには、案外、ピタリとはまる曲ではある。
・「夜想曲」
・「ペレアスとメリザンド」組曲
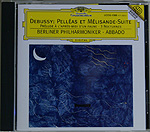
1999
ベルリン放送合唱団(夜想曲)
・「夜想曲」・・・楽団の技術と、各場面の描き分けやデュナーミク調整の巧みさなど演奏全体の「彫りの深さ」はボストン盤を上回る。ただ、指揮者にやや「元気がない」感じがするのが気になる。「祭り」はその典型で、事務的あるいは即物的には明らかにこのベルリン盤のほうが上なのだが、聴いていてどっちが心が躍るか、と言われたら、正直、ボストン盤のほうだと言わざるを得ない。
・「ペレアス〜」組曲・・・歌劇「ペレアスとメリザンド」の4つのシーンの音楽を、指揮者・エーリヒ・ラインズドルフが組曲にまとめたもの。
WPとの全曲よりも楽団が雄弁なのはそれぞれ演奏しているのが、「各独唱者を伴う全曲」なのか「管弦楽だけのこの4曲だけで、「ペレアス〜」とはどういう話なのかを伝えないといけない組曲」なのか、の違いであって、善悪や巧拙の違いではない。
別の言い方をすればこの「組曲」のほうが華やかである意味わかりやすい演奏だが、全曲版の、わけのわからなさ故の独特の深遠な魅力はない・・・でも、それも「別の曲だ」と思えば、作品にも編集者にも演奏者にも、別に何の問題もない。
本アルバムのメインを飾るに相応しい、充実した演奏である。
00289 477 5082
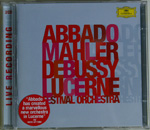
異様なまでに「厚く、太い」また派手に荒れ狂う、しかし確信と説得力に満ちた演奏。1970年頃のアバドにはもちろんのこと、1998〜99年頃のアバドにもできなかった演奏が、ここに、ごく自然に成立している。
少なくともCDで比較する限りは、併録されたマーラー以上に聴き応えのある演奏である。
・交響詩「海」
2053469
スイス室内合唱団(「聖セバスチャンの殉教」)
その中で、ドビュッシーの2曲を収録したこのDVDはかなり特異な地位を占めるわけだが、演奏は極めて優れている。
・「聖セバスチャンの殉教」・・・編成自体は大きいのだが、一般的なあるいは通俗的・外面的な意味で「迫力」のある作品とはいえない。でも2人の独唱者・男声合唱に女声合唱・オーケストラ内の各パートがそれぞれ点描するかのように繊細なしかし深く敬虔な音楽をつむぎあげていく様子はとてもスリリング。
率直に言って聴く側にとっても相応の集中力を要求される作品であり演奏だが、それは全く負担には感じない。程よい照明の演出も効果的。
・「海」・・・上のCDと同時期の収録なので基本的に同様の演奏だが、ここでは「うねるようなセクシーさ」も特徴として付け加えておく。また「荒れ狂うオーケストラ」ほどには、アバドの動きは大きくないことに目を見張らされる映像でもある。
なお、本DVDにはアバド/ルツェルンのリハーサル風景およびルツェルン音楽祭の歴史に関するドキュメンタリーも収録されている。
CDPB-254(CD-R盤)

繊細なしかし雄渾な音楽作り、的確なリズム感と絶妙のバランス調整。そしてなんといっても「シレーヌ」における力強い女声合唱団の圧倒的な存在感。
録音は決して良くないが、全盛期のアバド/LSOで、この曲の録音が、例え非正規でも残っていたのはしあわせなことではないか。
「ペレアスとメリザンド」
(CD3枚組)
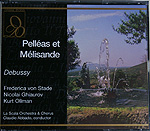
ブロッヒェラー(ゴロー)、ギャウロフ(アルケル)、
リノス(ジュヌヴィエーヴ)、パーチェ(イニョルド)、
ジャコモッティ(医者)
ミラノ・スカラ座合唱団
(もっとも、当時は日本のメディアでは「後任のMさん」が、既に事実上のスカラ座の主、と目されていたと記憶しているが。)
非正規盤とはいえ「1986年5月」なら、もっと録音状態は良くてもいいのではないか、と言いたくもなるが、演奏自体は悪くない。
WPよりも硬質で動きがあり、また独特のあくの強さと演劇的な緊張感を持つスカラ座管弦楽団の音を、他のスカラ座録音ではみられないこくの深い指揮で操るアバド、知的でやや翳があり、しかしチャーミングなメリザンドのフォン=シュターデは正規盤に負けず劣らず魅力的。
その一方でペレアスのオルマンは爽やかな声だがやや単調な歌唱。ゴローのブロッヒェラーはノーブルさよりも人間くささが際立つ歌唱・演技で、ある意味共感できなくもないが、人によって評価は分かれると思う・・・。
脇役陣ではジュヌヴィエーヴ役のリノスが若干非力な感じながらも手堅くまとめ、アルケルのギャウロフは声力の多少の衰えをも「高貴で力強く存在感のある」役作りに生かしているとさえ思える貫禄。
そしてWP/DG盤と唯一共通する歌手のパーチェ。当時22歳くらい。まだ稚ささえ感じさせる瑞々しい声が鮮烈だが、演技はまだちょっと・・・というところか。
繰り返すが、録音状態が良くないのが本当に惜しまれる。正規盤とは違った独自の魅力は十二分にあるといえよう。