| NO. | 楽団 | 曲名 | レーベル | 録音年 | 共演者等 | |
| 1 | ロンドン交響楽団 | ・交響曲第3番 イ短調 作品56「スコットランド」 ・交響曲第4番 イ長調 作品90「イタリア」 |
デッカ K20C8655(LP) 450 099-2 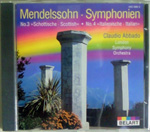 |
1967 | ||
| 1967年2月の録音。アバド初期にはデッカに入れたレコードが多いが、私がこの指揮者に関心を持ち始めた1980年代初期に同レーベルのアバドのレコードで現役盤だったのは確かこれだけ、だったような記憶がある。 でも・・・その後も現在に至るまで、この録音が「廃盤」になった時期はほとんどなかったような気もする。アバドの全録音の中で、一番の「ロングセラー」なのかも知れない。 それはともかくとして。 ・「第3番」 デッカ録音のせいもあるかも知れないが、基本的にソリッドな音。指揮はやや慎重というか腰が重い。その一方で生硬かつ単調なところもあるものの、のちのDG録音に比べると全体的にスリムに引き締まっており、独自の良さのある演奏とは思う。 ・「第4番」 全体的な特徴は「第3番」と共通。各パートともやや古びた・鄙びた感じの楽団の音色がとても個性的で、それがアバドの品の良いテンポもいい指揮と相まって曲の随所で深い陰影を形成していることに、これもまた独特の魅力がある。 2曲とも「アバドの」指揮・演奏として聴けは、84年のDG録音のほうが明らかにいいと思う。 でも「この2曲の」演奏として聴いた場合には、あえて、こっちの録音のほうを採る、という人がいたとしても決しておかしくはないとも思う。 (なお、私が持っているCDは、一時期、DG・デッカ・フィリップスの共通廉価盤レーベルとして用いられていた「BELART」から出ているもの。 正直、「オリジナルズ」で聴き直したい気もあるが・・・。) |
||||||
| 2 | ウィーンフィル | ・ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 | DG 20MG0312(LP) 419 067-2 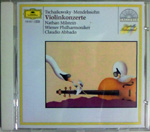 |
1972 | ミルシテイン | |
| 「メン・チャイ」という用語は今では”死語”だろうか・・・。ともあれ、LPもCDもそのカップリング。 デリケートかつチャーミングな、あるいは上品な媚態にあふれた独奏者と、ややスケールは小さいながらも楽団の美音を生かしてこれまた上品で繊細な伴奏の指揮者。 いずれにせよ過不足なくまとまり過ぎな感も否めないものの、 クラシック音楽のジャンルを代表する(していた)名曲の、ある意味「模範的な」好演として多くの人に薦めるには最適な演奏・録音とも思う。 (カップリングされた「チャイ」のほうは、独奏者・指揮者とも、この「メン」よりはよくも悪しくもあくの強さが(若干だが)出ているのだが。) |
||||||
| 3 | シカゴ交響楽団 | ・ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 | DG 00289 477 6349  |
1980 | ミンツ | |
| 同じ演奏者たちによるブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番と、ミンツ/ベンスン(pf)によるクライスラー小品集を併録。LP時代のオリジナルカップリングは「メン・ブル」の2曲だったが、このLPはいつか買おうと思っているうちに買い逃し、CDになってからもなかなか買う順番が回らず、数年前にやっと入手した。 ミンツの独奏は優しく甘美だがやや固さも感じられ、のちにアバドと共演したプロコフィエフやブラームスの場合ほどの自在さや説得力はない。一方、上のミルシテイン盤では「室内楽」的ともいえたアバドの伴奏指揮はこっちではシンフォニックでスケールも大きい。緊張気味の若い独奏者を、当時は中堅の域に達していた指揮者が頼もしくサポートする雰囲気は特に第2楽章で顕著。 総合的に演奏としてしっかりしているのは明らかにミルシテイン盤のほうだが「聴いていて楽しい」のは・・・こっち、ということにしておく。 |
||||||
| 4 | ロンドン交響楽団 | 「交響曲全集・序曲集」 1・交響曲第1番 ハ短調 作品11 2・スケルツォ ト短調(弦楽八重奏曲 作品20から) 3・序曲「真夏の夜の夢」 作品21 4・序曲「フィンガルの洞窟(ヘブリディーズ諸島)」作品26 (以上CD1) 5・交響曲第2番 変ロ長調 作品52「賛歌」 (以上CD2) 6・交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」 7・序曲「美しいメルジーネの物語」 作品32 (以上CD3) 8・交響曲第4番 イ長調 作品90「イタリア」 9・交響曲第5番 ニ長調 作品107「宗教改革」 (以上CD4) |
DG F00G50286〜9 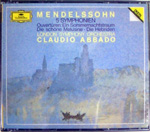 |
1984 1985 |
コンネル マッティッラ ブロックヴィツ (独唱者の日本語表記は 本CDの解説書に従った。) ロンドン交響合唱団 |
|
| 国内盤CD初出時(1986年春)のオリジナルな収録曲と曲順は上記のとおり。その後現在に至るまで分売も含めて様々な形で発売されている。 「交響曲全集」というと曲によって演奏の出来に差があったり、その演奏者に合っている曲とそうでない曲がなんとなくわかってしまったりするようなことも少なくないわけだが、本全集は比較的短期間に集中して録音されていることと、「すべての曲がこの指揮者には合っている(笑)」こととによって、とても上質の「全集」となっている。 ・「第1番」・・・曲自体の構成や進行には未熟さが感じられる作品だが、アバドの指揮はその「弱点」をあえて隠そうとはせずに、逆にそれを若きメンデルスゾーンの旺盛な表現意欲として聴かせてくれている。 ・スケルツォ・・・「交響曲第1番第3楽章の代替可能曲として作曲者自身が編曲」。実際メンデルスゾーン自身の指揮でそのような形態で演奏されたこともあるそうだが、それをやると「この楽章だけが妙にレベルが高い」ことになってバランスを崩すのでは?との懸念もなくはない。ともあれ、程よく抑制されたリズミカルな、アバドらしい演奏。 ・序曲「真夏の夜の夢」・・・明るく開けっ広げな、それでいて隅々まで神経の行き届いた名演。特に、デュナーミクと音色の微妙な調整とめくるめく曲想の変化とをシンクロさせる手際のよさはアバドの全録音の中でも最高水準。 ・・・後でも触れる(触れざるを得ない)が、私は、この曲のLSO盤と、後述の「6」のBP盤を聴きくらべたときに、 「なぜ、BP音楽監督としてのアバドはとやかく言われた(言われる)のか」「なぜ、LSO時代のアバドは評判がいいのか」 について、一番手っ取り早く実感、というより「納得」することができる、と正直に言っておく。 ・序曲「フィンガルの洞窟」・・・演奏の基本的特徴は前曲と同じ。表面的な派手さや華やかさを抑制しつつこれだけの表情豊かな、品格あるエモーショナルな演奏を実現しているという意味では、むしろこっちのほうがより高レベルの演奏と言えるかも知れない。 なお、本セットではこの曲だけが1985年(2月)の収録のようである。 ・「第2番」・・・重厚で優しいオーケストラの響き、若々しい活力にあふれる独唱者と合唱団、第6曲(テノール独唱から、ソブラノの「Die Nacht ist vergangen」まで)〜第7曲(合唱と管弦楽)〜第8曲(コラール)の流れに象徴される、敬虔さと劇的迫力のみごとな両立・・・ほんとは「交響曲」ではないかも知れない曲だが、本全集中では私の一番好きな曲であり、演奏である。 ・「第3番」・・・67年盤と比べればはるかにスケールの大きな、また「しなやかな」指揮。やや暗めの品位のある曲想をしっかりと生かした適度なしかし物足りなさを感じさせることのない劇的な演奏で生かしきっている。第3楽章の優しくも力強い音楽の進行を支える迷いのない指揮の説得力は特に素晴らしい。 楽団の音色も色彩感あふれる輝かしいものに変化している(が、ここに限れば人によっては67年盤を採るかも知れない・・・)。 ・序曲「美しいメルジーネ〜」・・・基本的には穏やかな、そして繊細で澄み切った演奏。各場面の描き分けも巧み。また、この曲を「スコットランド」の後に、同じCDに収録した、というセンスの良さもほめてあげたい。 ・「第4番」・・・67年のデッカ盤と比べた場合、リズム感もノリも良くなっているし、それらも含めてフレージングの自然な伸びやかさの点でこちらのほうがはるかに充実感あふれる指揮。自然に呼吸するかのような違和感のない演奏でもある。 ただ楽団の音色の自体については「第3番」と同様のことが67年盤との比較では出てくる余地も十分にあると正直思う。 ・「第5番」・・・曲自体の出来や魅力は、「スコットランド」や「イタリア」に比べれば多少劣るのかもしれない。でも演奏は全4楽章を通した堅牢な構成力の点で本全集中の他曲に対し決してひけはとらない。温和な快活さと明朗な歌謡性という(特にこの頃の)アバドの特徴が、穏健さとバランスのよさの奥深くに芯の強さを感じるメンデルスゾーンの作品といかに相性が良いかを端的に示している。 |
||||||
| 5 | ロンドン交響楽団 | 「序曲集」 1・序曲「美しいメルジーネの物語」 作品32 2・序曲「真夏の夜の夢」 作品21 3・序曲「静かな海と楽しい航海」 作品27 4・「吹奏楽のための序曲」 作品24 5・「トランペット序曲」 作品101 6・序曲「ルイ・ブラス」 作品95 7・序曲「フィンガルの洞窟(ヘブリディーズ諸島)」作品26 |
DG 423 104-2  |
1984 1985 1986 |
||
|
「演奏時間10分前後の良質の超短編オペラ」の如き演奏が7曲連続するかのようなアルバム。 各作品の特徴をそれぞれ明確に明確に描き分けた上に演奏のクオリティも高いレベルでほぼ統一されている。 1.2.7の3曲は、上記「4」の交響曲全集に入っているのと同じ演奏なので、ここでは他の4曲について。 ・序曲「静かな海と楽しい航海」・・・「海の凪と成功した航海」と訳したほうがいいのかどうかはよくわからない(苦笑)。 「静かな海」部分の深く幻想的な雰囲気と「楽しい航海」部分の明朗快活で現実的なダイナミズムのそれぞれを生き生きとした鮮やかなコントラストで描き出した上に両者をみごとに両立・融合させた名演。 トランペットのファンファーレのあと、終曲直前の「静かな海」部分の短い回想が深く心地よい余韻を与えてくれるのがまたいい。 ・「吹奏楽のための序曲」・・・前半の温和なアンダンテ部分でためていた力を、後半のアレグロ・ヴィヴァーチェで一気に開放する。シンプルな曲想だが、それを小細工無しにストレートに生かした楽しくまたカッコいい演奏。LSOの管楽セクションの芸達者ぶりもご堪能あれ。 ・「トランペット序曲」・・・モーツァルト的と言ってもいいくらいの明朗・端整で古典的な曲想を基本に、いい意味で敷居が低いというか人間くさい親しみやすさの強い表情付けがなされた作品をアバドがいつも以上に華麗にまた大らかに再現。 なお、題名から連想されるほど「トランペットが大活躍する」わけでは決してない。念のため。 ・序曲「ルイ・ブラス」・・・私が持っているこのCDが日本盤でなかったというだけの理由だが、ユーゴーの『リュイ・ブラース』のあらすじについてはWikipediaで今回初めて調べてみた・・・この戯曲をメンデルスゾーンには気に入らなかったらしい、と言われると確かにそういう内容かな、とも思ったが、曲は劇的な激しさを格調高くまとめあげたなかなかの傑作。アバド/LSOも重厚にしかし情熱的な演奏で応じている。 |
||||||
| 6 | ベルリンフィル | 1・序曲「真夏の夜の夢」 作品21 2・劇音楽「真夏の夜の夢」 作品61(抜粋) 3・交響曲第4番 イ長調 作品90「イタリア」 |
ソニー SRCR1620  |
1995 | スコーヴァ マクネアー キルヒシュラーガー エルンスト・ゼンフ合唱団 |
|
| 1995年のジルヴェスターコンサートのライブ。 ・「作品21」・・・大変申し訳ないが、上記「4」や「5」のLSO盤で同曲の演奏を聴いたあとではこのBP盤は聴けない。テンポ感やデュナーミク変化の大味さに加えて各パート間のバランスの悪さには正直閉口せざるを得ない。 ・「作品61(抜粋)」・・・スコーヴァの語りと繊細な女声合唱が魅力的。指揮と楽団は・・・作品21よりは表情豊かだが、全体的には意外なほどに平板な印象を拭えない。 ・「交響曲第4番」・・・本アルバムでは一番良い演奏。だが・・・楽団はLSOよりも上手い、というかずっと上手い。アバドの指揮も84年DG盤よりもさらにこなれて流麗。それなのに、演奏の魅力は、過去の2種のLSO盤のほうが、上、だと思う。 豪奢だがやや粗く、軽快というよりは「軽い(否定的な意味で)」音、と、この頃のアバド/BPを私が語るときの常套句がここでも出てしまうのは残念だが、それでもこの曲の場合は多分に指揮者と作曲家(作品)との相性の良さで救われているところも多い。 |
||||||
| (2011年6月12日〜6月26日のあいだに大改訂) | ||||||
| 以下は、非正規盤。 | ||||||
| 7 | シカゴ交響楽団 | 交響曲第5番 ニ長調 作品107「宗教改革」 | LIVE CLASSIC BEST LCB135 |
1986 | ||
| ムーティ/WPの「スコットランド」「イタリア」、シッパーズ/RAIローマSOの序曲集とのカップリング。 「異なる演奏家による同じ作曲家の作品を1セットにまとめた」LCBらしい(?)2枚組。 アバド/CSOの「宗教改革」は、1986年、ロンドンでの録音とのこと。 DG/LSOの全集盤の同曲と比べた場合には録音状態の悪さのせいもあってか緻密さには欠けるものの全体的に彫の深い重みのある解釈を聴くことができる。また終楽章の、アバドらしい「前のめりのラッシュ」は極めてエキサイティング。 |
||||||
| (7のみ、2011年12月6日追記) | ||||||